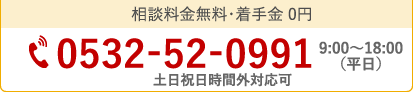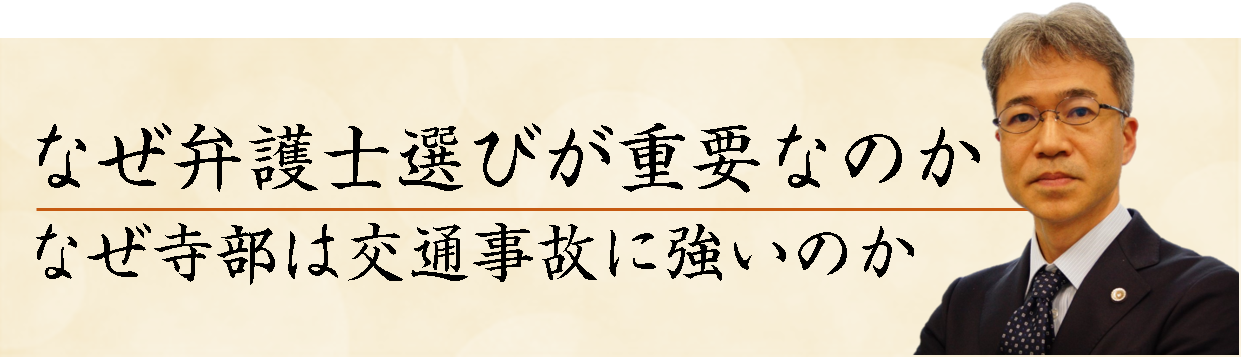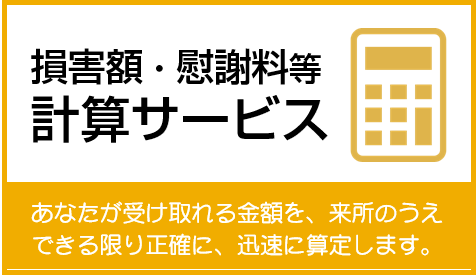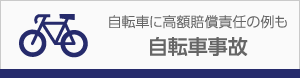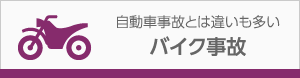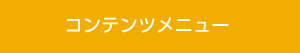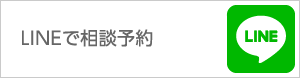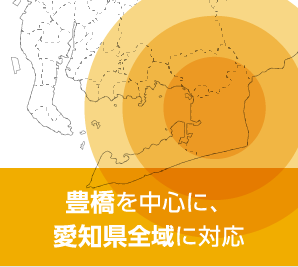新着情報
年金と遺失利益
死亡事故の場合、交通事故がなく、被害者が生きていたのであれば得られたであろう経済的利益について、損害に含めて請求することができます。
死亡逸失利益は、基本的には、基礎収入×(1ー生活費控除率)×基礎収入を得ることができたであろう期間に対応するライプニッツ係数という計算により算出します。
ところで、死亡事故の被害者が年金を受給していた場合、年金については、逸失利益の基礎収入に含まれるのでしょうか
続きを読む >>
後遺症慰謝料
交通事故によって傷害を負い、治療した結果、後遺障害が残った場合には、傷害慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料が認められる場合があります。
後遺障害慰謝料については、
自賠責保険の後遺障害等級表に該当する場合に認められることが一般です。
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険の後遺障害等級表(1級から14級まであります)の何級に該当するかが、大きな要素となります。
後遺障害慰謝料は、自賠責保険の後遺
続きを読む >>
交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効などについて
交通事故の被害者の方は、加害者に対し、いつまで、損害賠償請求をすることができるのでしょうか。
交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の法的な性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権と考えられます。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条前段)。
なお、民法724条後段は、不法行為の時
続きを読む >>
損害賠償請求の相手方
自動車の運転者の過失による交通事故によりけがをした被害者の方は、誰に対し、どのような法的根拠で損害賠償請求をすることができるのでしょうか。
まず、自動車の運転者に対し、民法709条に基づき、損害賠償請求をすることが考えられます。
次に、運転者が、従業員など被用者である場合、民法715条1項に基づき、使用者に対し、 損害賠償請求をすることが考えられます。タクシー会社の運転手が、タクシー車両を業務
続きを読む >>
傷害慰謝料について
交通事故により身体が毀損された場合には、一般的には慰謝料が請求できます。実際に外傷を負った場合だけでなく、他覚所見のないむちうち症状など、外傷のない場合も一般的には請求できます。
この慰謝料には、実際に傷害を負ったことによる肉体的な苦痛のほか、治療などのため入院や通院をしたことによる精神的な苦痛もその要素に含まれます。
傷害慰謝料については、基本的には入院、通院の期間が重要な要素になります
続きを読む >>
家事従事者の場合の逸失利益
家事従事者が交通事故で死亡した場合の逸失利益は、どのように計算するのでしょうか。ここでは、基礎収入をどのように考えるかを説明します。
一般的には、女性労働者の平均賃金をもとに計算すると考えられています。平均賃金は、一般的には、賃金センサスという統計資料を用いて、その産業計、企業規模計、学歴計の平均賃金の数字を用います。全年齢平均賃金を用いることが多いですが、事案によっては、年齢別平均賃金を用いる
続きを読む >>
過失相殺
交通事故の損害賠償請求について、損害額が全額請求できるとは限りません。
被害者側にも一定の過失が認められ、損害額の一定割合が差し引かれる場合があります。これを過失相殺といいます。
青信号にしたがって横断歩道を横断中の歩行者と信号無視の自動車の交通事故の場合、一般的に歩行者側には過失が認められません。
また、自動車を運転中、赤信号にしたがって停車中に後方から進行してきた自動車に追突された場合に
続きを読む >>
弁護士費用特約
最近、ご相談のなかで、弁護士費用特約を利用して弁護士を依頼したいとのお話をいただく場合があります。
弁護士費用特約の利用については、ご相談者の加入されている保険会社に確認をしていただいたうえで、弁護士までお伝えください。
弁護士費用特約の利用した示談交渉などは、当事務所でも取り扱わせていただいております。
なお、弁護士費用特約を利用した場合の当事務所の報酬基準については、完全成功報酬制ではあ
続きを読む >>
死亡慰謝料
交通事故の被害者の方が交通事故により死亡した場合、被害者の法定相続人の方は、一般的に死亡による慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、被害者の方と法定相続人との関係等や当該事案の個別事情によって異なりますが、2000万円~2800万円のケースが多いと考えられます。なお、この慰謝料の金額は、死亡した被害者の慰謝料請求権の相続のほか、民法第711条の規定、これに準じる者の固有の慰謝料請求権
続きを読む >>
死亡による逸失利益
死亡による逸失利益は、一般的に、基礎収入額×(1ー生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ計数によって計算します。
基礎収入額は、実際に働いている方は、事故前の収入額を基準にしますが、賃金センサスの数字を用いる場合もあります。
死亡による逸失利益の計算にあたっては、後遺症による逸失利益の計算の場合と異なり、死亡した被害者は、生活費を支出することはなくなるため、生活費を控除することが必要に
続きを読む >>