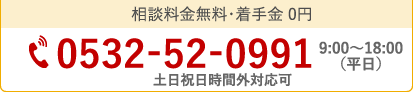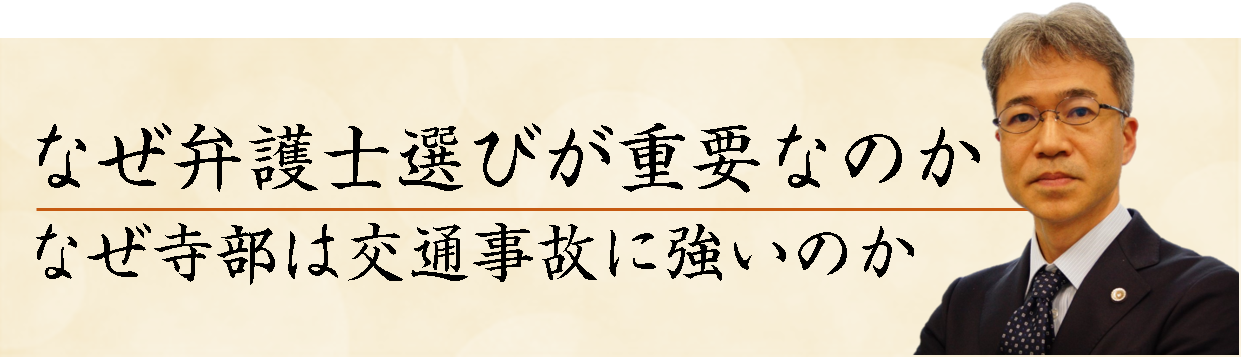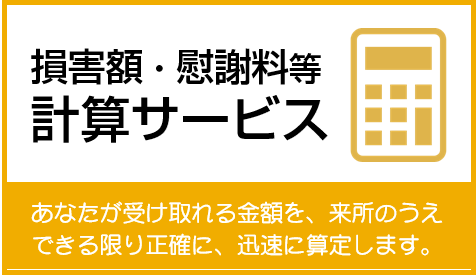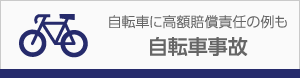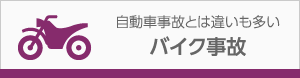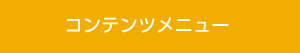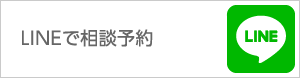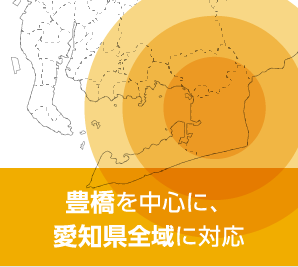高次脳機能障害とは
1 軽度な高次脳機能障害
軽度な高次脳機能障害の場合、被害者の方に自覚症状がない場合があります。
被害者の方に自覚症状がなく、その一方で、ご家族の方は、
普段と違うと感じている場合、医師にその症状が伝わらず、
診断書等に何の記載のないまま治療が進行したり、
医師が症状を認識できないために必要な検査等が行われない可能性があります。
例えば、高次脳機能障害の症状の一つとして、
怒りっぽくなるという症状が現れる可能性がありますが、
この症状を被害者の方自身が自覚することは、多くの場合困難だと思います。
診断書に実際の症状等が記載されなかったり、必要な検査等が行われなかった場合、
後の後遺障害の認定などに影響を及ぼす可能性があります。
ご家族の方が、ご本人に交通事故の前と比べて、違うところがあると感じた場合には、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
2 遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害の損害賠償と将来の介護費用
遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害を理由に後遺障害が認定された場合、
後遺障害分の損害として、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が問題となります。
また、遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害の場合、損害賠償として、
将来の介護費が問題となる場合があります。
将来の介護費については、介護の必要性、家族による介護なのか、
職業付き添い人による介護が必要なのか、など様々な問題が生じます。
遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害の損害賠償については、
弁護士までご相談されてはいかがでしょうか。
3 弁護士への早期依頼のメリット
①保険会社との対応
遷延性意識障害、重度の高次脳機能障害の被害にあった場合、
ご家族の方にとっては、被害者の方の介護などで大変な状況であることが多いと思います。
そのような状況の中で、保険会社との対応をしなければならないことは、
大変なことが多いと思います。
弁護士に依頼をすれば、保険会社とのやりとりは、弁護士が行います。
その結果、被害者の方やそのご家族の方は、
治療や介護に集中できる場合が多いと思います。
②将来の後遺障害認定、損害賠償に向けたアドバイス
早期に弁護士に依頼すれば、遷延性意識障害、高次脳機能障害については、
後の後遺障害等級認定、損害賠償を見据えて、アドバイスを受けることもできます。
③過失相殺がある事案
交通事故で被害者にも過失がある場合には、過失相殺という制度があり、
通常、被害者の過失に応じて、損害賠償額が減額されます。
遷延性意識障害、高次脳機能障害がある場合には、損害賠償額が高額になる場合があり、例えば、10パーセントの過失であっても、金額として高額になる可能性もあります。
過失相殺についても、慎重に対応する必要があります。
④まとめ
交通事故の被害にあった場合には、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士 寺部光敏
最新記事 by 弁護士 寺部光敏 (全て見る)
- 自動車を運転中、信号無視の自動車と交差点内で接触した交通事故により、頚椎捻挫、胸椎部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負い、示談交渉により、慰謝料が増額になった事例 - 2024年12月30日
- 交通事故の後遺症等級認定の手続きをすると、損害賠償請求権について、時効の更新(中断)になりますか? - 2023年12月10日
- 交通事故の損害賠償において、専業主夫の場合も、休業損害を請求できますか? - 2023年12月4日
- 交通事故の被害者が、通院中、MRIを撮影するために他の病院に通院する場合、どうすればよいですか? - 2023年9月22日
- パートとして働いている主婦が、交通事故の損害賠償について、主婦としての休業損害を主張することができるのでしょうか? - 2023年8月10日