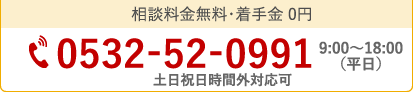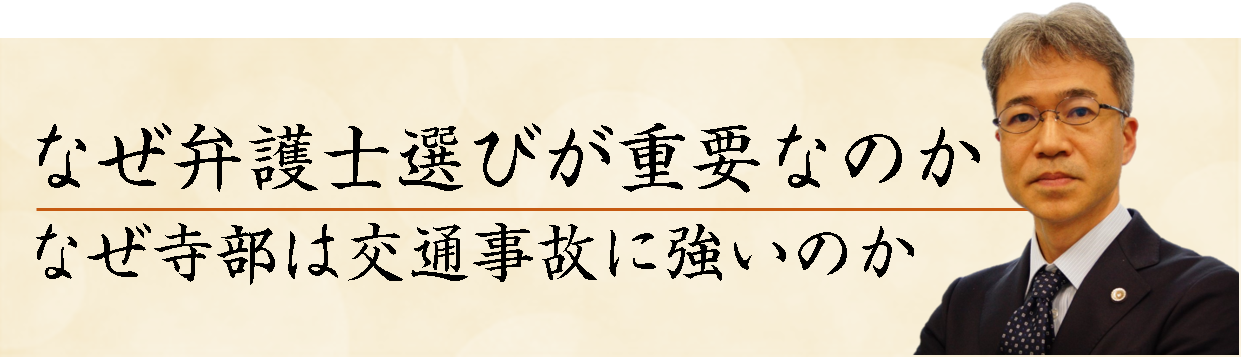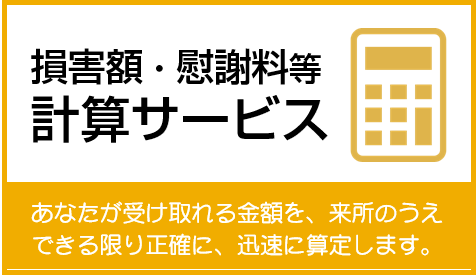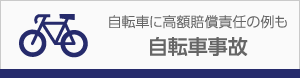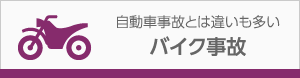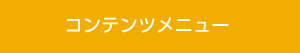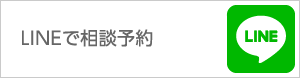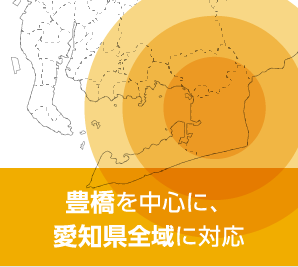新着情報
交通事故と慰謝料
1 はじめに
交通事故によって傷害を負った場合、傷害を負った苦痛に対する慰謝料が問題となります。
また、交通事故によって傷害を負い、治療終了後も後遺障害が残り、自賠責後遺障害別等級記載の後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が問題となります。
具体的な事例をもとに、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、説明したいと思います。なお、事例は、フィクションです。
2 事例
続きを読む >>
交通事故と示談
1 はじめに
交通事故の人身損害について、示談をすると、どのような効力があるのでしょうか。
次のような事例を想定して説明します。
2 事例
Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、整形外科に約8ヶ月通院し、症状固定となりました。
Aさんは、後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きをしたところ、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号(
続きを読む >>
後遺障害(後遺症)と外貌醜状
交通事故によって傷害を負い、症状固定後も外貌に醜状が残った場合には、後遺障害(後遺症)が認定される場合があります。
外貌醜状に関する後遺障害としては、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)、第9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)、第12級14号(外貌に醜状を残すもの)があります。
後遺障害が認定されれば、多くの場合、慰謝料と後遺障害逸失利益が問題
続きを読む >>
共同不法行為と求償
民法719条は、共同不法行為について、規定しています。
タクシー会社(A)の運転手(B)が運転するタクシーと、Cが運転する自動車が衝突し、タクシーに乗車中の乗客(D)が傷害を負った場合、BとCの共同不法行為に該当する場合があります。
この場合、タクシー会社(A)が、乗客(D)に対し、Dの損害を賠償した場合、Aは、Cに対し、求償をすることはできるのでしょうか。
この問題に関し、最高裁判所の裁判
続きを読む >>
一部請求と過失相殺
損害賠償請求訴訟において、損害の一部を請求し、相手方から過失相殺の主張をされた場合、過失相殺はどのように計算するのでしょうか。
この点について、最高裁判所の裁判例には、
「一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたっては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは、右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容す
続きを読む >>
シートベルト不着用と交通事故の過失相殺
道路交通法第71条の3第2項本文は、
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る)に乗車させて自動車を運転してはならない」旨規定しています。
したがって、自動車の後部座席に乗車する場合も、原則としてシートベルトの装着が義務になります。
交通事故が発生した場合、後部座席に乗車していた場合
続きを読む >>
高次脳機能障害
交通事故により、頭部に衝撃が加わり、高次の脳機能に障害が生じる
場合があります。
高次脳機能障害の典型的な症状として、認知障害、行動傷害、人格変化などが
指摘されています。
高次脳機能障害となった結果、後遺障害に該当する場合もあります。
自賠責保険の後遺障害の等級認定と訴訟における後遺障害の等級は、
同じことが多いです。もっとも、事案によっては、違う場合もあります。
下級審
続きを読む >>
物損事故と損害
物損事故において、どのような損害が賠償の対象となるのでしょうか。
物損の典型的な例は、交通事故により自動車が損傷した場合です。
この場合、修理が可能であれば、原則として、修理代が損害になります。
もっとも、自動車の修理代が交通事故の被害にあった自動車の時価より高い場合には、原則として、交通事故の被害にあった自動車の時価が損害となると考えられます。
また、自動車の損害として、評価損が問題
続きを読む >>
物損事故と評価損(格落ち損)
物損事故において、多くの場合、自動車が損傷して、修理が必要になります。
交通事故の被害に遭い、修理によって自動車としての機能が回復したものの、一度、修理をすると、いわゆる事故車として、中古車市場における取引価格が下がる場合があります。
このような評価損(格落ち損)を交通事故の損害として、請求できるのでしょうか。
下級審の裁判例ですが、
「本件においては、修理完了後も自動車の性能、外観等
続きを読む >>