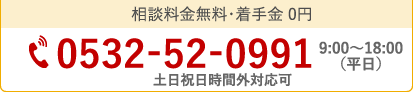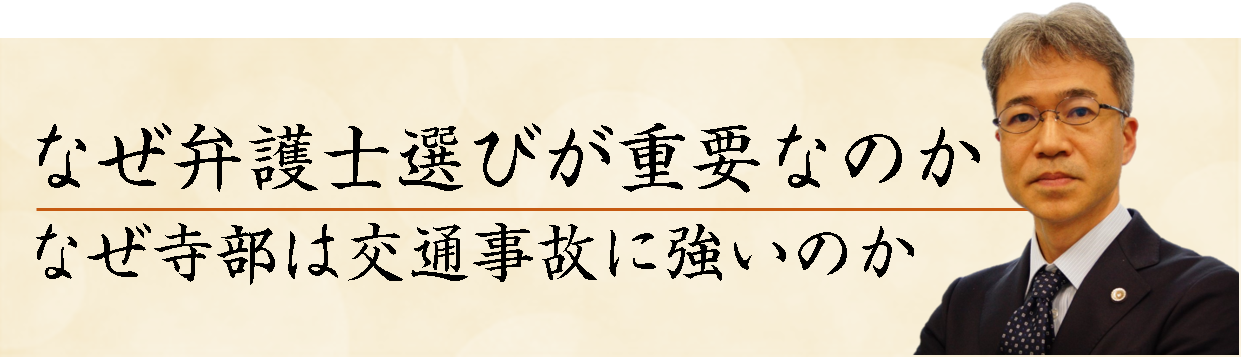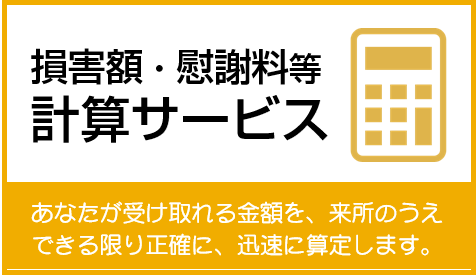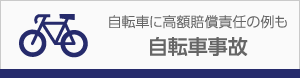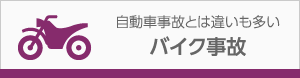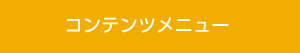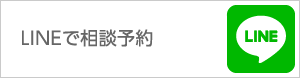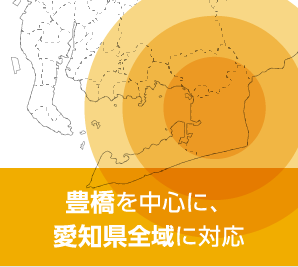交通事故を弁護士に相談、依頼するタイミングとは?

1 はじめに
交通事故の被害者の方が、弁護士に交通事故を相談、依頼するタイミングは、どのように考えたら良いのでしょうか?
ここでは、交通事故の加害者が対人無制限の任意保険に加入しており、被害者の方に過失がないことを前提に説明します。
2 交通事故発生から示談までの流れ
交通事故の発生から示談の成立までの流れは、次のようになることが多いです。
なお、個別の事案によっては、異なる場合もあります。また、示談が成立せずに訴訟になる場合もあります。
①交通事故発生
交通事故が発生した場合、自動車を安全な場所に止めてエンジンを切る、怪我をした方がいる場合は救護措置をしたり、警察へ連絡したり、保険会社、保険代理店へ連絡するなどの必要な措置をします。
②治療
交通事故によって負った怪我の治療をします。
③症状固定
症状固定とは、治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態をいいます。
症状固定となると、相手方保険会社が治療費を負担する形での治療は、終了します。
症状固定後の治療は、原則として、自己負担になります。
④後遺障害がない場合
症状固定となり、後遺障害がない場合には、示談交渉をします。
⑤後遺障害の等級認定手続をする場合
後遺障害の等級認定をする場合、事前認定という方法と被害者請求という方法があります。
事前認定とは、相手方の任意保険の保険会社を介して、後遺障害の等級認定の手続をする方法です。
被害者請求とは、相手方の自賠責保険会社を介して後遺障害の等級認定を受ける方法をいいます。
⑥示談交渉
後遺障害がない場合や、後遺障害の等級認定の手続をして、結果がでた場合には、示談交渉をします。
⑦示談成立
示談交渉の結果、合意に達した場合には、書面に署名、押印をして、示談が成立します。 ⑧示談金の支払い
合意に基づき、損害賠償金が支払われます。
3 弁護士に相談、依頼するタイミング
交通事故発生から、示談が成立する前までであれば、いつでもご相談、ご依頼をすることができます。
示談が成立してしまうと、通常、示談の内容を覆すことはできません。
示談が成立した後に、よく調べたら、自賠責基準で示談してしまったという場合であっても、通常、示談の内容を覆すことができません。
遅くとも、示談書にサインをする前に、弁護士までご相談ください。
4 弁護士に早期に相談、依頼するメリット
(1)弁護士に相談する一番良いタイミングは、交通事故直後だと思います。
とりあえず、相談だけをしておけば、後に依頼する場合にスムーズに話が進むと思います。
交通事故を多く扱っている弁護士は、交通事故の示談交渉や訴訟などを多く経験しています。そうした経験をもとに、相手方保険会社への対応や医療機関の通院について、助言を受けることができます。
(2)弁護士に依頼するタイミング
①治療中
治療中にご依頼を受ければ、弁護士がご依頼者の方に助言をしながら、相手方保険会社との間でやりとりをします。
なお、弁護士費用特約に加入している場合、当事務所では、通常、示談交渉の限りでは、弁護士費用特約の範囲を超えて、ご依頼者の方にご負担をお願いすることはありません。 早期に弁護士にご依頼をされても、通常、ご依頼者の方の負担が増えることはありません。
②相手方保険会社からそろそろ症状固定との連絡が入った
相手方保険会社から、症状固定について、連絡が入った場合、弁護士に依頼するタイミングのひとつだと思います。
症状固定後の治療費は、原則として、自己負担となりますので、症状固定の時期は、節目になると思います。
③後遺障害が認められなかった
後遺障害の等級認定の手続の結果、後遺障害が認められなかった場合、弁護士に依頼するタイミングのひとつだと思います。
後遺障害の等級認定の結果に対し、異議を申し立てるか、検討をします。
④相手方保険会社の提示する示談額に納得がいかない
相手方保険会社の提示する示談額に納得がいかない場合、弁護士に依頼するタイミングのひとつだと思います。示談書に署名、押印してしまうと、後に、示談の効力を争うことは、原則として、できなくなります。
弁護士費用特約がない場合であっても、当事務所では、示談交渉の場合、相手方保険会社の提示額からの増額を基準として、弁護士費用を計算しますので、通常、弁護士費用が増額分を上回ることはありません。
5 弁護士に依頼した場合の相手方保険会社に対する対応
(1)受任通知の発送
弁護士が受任をすると、弁護士は、相手方保険会社に対し、受任通知を発送します。
弁護士が委任を受けた後は、弁護士を通じて相手方保険会社とやりとりをします。
(2)治療中の対応
ご依頼者の方が治療中、相手方保険会社から、定期的に治療内容や自覚症状などの問い合わせがあることが多いです。
弁護士から、治療内容や自覚症状などを確認させていただき、相手方保険会社に連絡します。
(3)症状固定
症状固定(治療を続けても、症状が改善しない状態をいいます、症状固定となると、その後の治療費は、原則、被害者の方の負担となります)時期が近づくと、相手方保険会社から連絡があることが通常です。
症状固定に関する連絡が入りましたら、ご依頼者の方に状況を確認させていただき、状況によっては、治療終了時期について、相手方保険会社と交渉をする場合もあります。
(4)後遺障害の等級認定
症状固定となった時点において、痛みその他の症状が残っている場合には、後遺障害の等級認定の手続を検討します。
(5)示談交渉
症状固定となって後遺障害の等級認定の手続をしないとき、後遺障害の等級認定の手続をして、後遺障害が確定したときには、弁護士が相手方保険会社と示談交渉をします。
弁護士は、裁判基準を目指して、相手方保険会社と示談交渉をします。
(6)示談成立
示談が成立すると、書面を取り交わし、相手方保険会社から損害賠償金を受け取ります。
6 まとめ
交通事故の被害にあわれた場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
弁護士 寺部光敏
最新記事 by 弁護士 寺部光敏 (全て見る)
- 交通事故、示談金は、いつ振り込まれる?交通事故発生から示談金がもらえるまでの流れを弁護士が解説 - 2025年10月30日
- バイク事故による損害賠償の増額方法に関して弁護士が解説 - 2025年9月2日
- バイクで交通事故にあった場合の対処法を弁護士が解説 - 2025年7月22日
- 交通事故後は、どのくらいの頻度で病院に通うべきですか? - 2025年7月7日
- 自動車を運転中、信号無視の自動車と交差点内で接触した交通事故により、頚椎捻挫、胸椎部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負い、示談交渉により、慰謝料が増額になった事例 - 2024年12月30日